『プラン75』予告編
『プラン75』解説〜どんな映画?
『プラン75』スタッフ・キャスト
監督・脚本:早川千絵/撮影:浦田秀穂
キャスト:倍賞千恵子(角谷ミチ…ホテル清掃員)/磯村勇斗(岡部ヒロム…市役所職員) /ステファニー・アリアン(マリア…「PLAN 75」関連施設従業員) /たかお鷹(岡部幸夫…ヒロムの叔父)/河合優実(成宮瑶子…PLAN 75コールセンター職員) 他
『プラン75』あらすじネタバレあり
夫と死別してひとりで慎ましく暮らす、角谷ミチ(倍賞千恵子)は78歳。ある日、高齢を理由にホテルの客室清掃の仕事を突然解雇される。住む場所をも失いそうになった彼女は<プラン75>の申請を検討し始める。一方、市役所の<プラン75>の申請窓口で働くヒロム、死を選んだお年寄りに“その日”が来る直前までサポートするコールセンタースタッフの瑶子(河合優実)は、このシステムの存在に強い疑問を抱いていく。また、フィリピンから単身来日した介護職のマリア(ステファニー・アリアン)は幼い娘の手術費用を稼ぐため、より高給の<プラン75>関連施設に転職。利用者の遺品処理など、複雑な思いを抱えて作業に勤しむ日々を送る。
果たして、<プラン75>に翻弄される人々が最後に見出した答えとは―――。
『プラン75』ネタバレ結末・閲覧注意!
『プラン75』考察〜誰かと話したくなる映画
『プラン75』考察〜78歳のミチの静けさ〜ネタバレあり
主人公の独居老人角谷ミチを演じたのは、倍賞千恵子です。
倍賞千恵子といえば、「寅さんシリーズ」はじめ、監督山田洋二作品に欠かせない庶民派女優という印象です。
寅さんシリーズでは「明るく優しいさくら」を演じて50本、いい意味で、そんな倍賞千恵子だから演じられた「独居老人ミチ」のように思えます。
ミチは、ホテル清掃員の職を辞めなければならなくなり、78歳という高齢を理由で収入の道が閉ざされます。
78歳の女性を再雇用する会社は見つからず、家賃が払えなくなっていく、、、そんなくだりがリアルすぎます。
ぼく自身、固定給がなく「一寸先は闇」のフリーランス絵描きなので、ほんと、リアルに迫ってきました。
ドラマでは頼る親族のいないミチは、やるせない思いを抑え込みつつ、結局「プラン75」書類にハンコを押すんですよね。
この「我が心情を抑え込む」って、いい意味でも悪い意味でも非常に日本人的で、これまたリアリティありすぎなんです。
そんなミチの姿はまるで、寅さんを見守っていた優しい妹さくらの、別の老後=一つのパラレルワールドのようにも思えてしまいました。
劇中で、一人暮らしのミチは、過去には結婚していた時期もあった…と明かされます。
しかし、様々ないきさつの結果、一人で生きていくしか道がなかった女性なんですね。
そんな彼女が、老いたのちに選ぶ選択肢は、「行政が法的に75歳以上の安楽死選択を認めるプラン75」しか残されていないという怖さにゾッとしました。
人って、人生の中で、誰もが「分かれ道」を体験しますよね。
でも、「分かれ道」は、2本あるから「分かれる道」なんですよね。
ミチが「プラン75」書類にハンコを押した理由は、捺印しなければ路上生活者になるしか道がなかったから…なんです。
ネタバレになりますが、ミチは、クライマックスにおいてプラン75安楽死施設で安楽死することに「No」を突きつけ、「それでも生きる」というもう一本の道を見出し、歩き始めます。
しかし、それって道なき道=イバラの道に他ならないじゃないか、、、と、ぼくはやるせない思いになりました。
そして、こう思ったのです。
「どん詰まりにぶち当たり、どうしていいかわからなくなった市井の人々に対し、気がつかなかったもう一本の道を指し示してくれるのが本来の行政ではないか??」
ぼくは映画『プラン75』のラスト、ミチの姿からそんなメッセージを受け取りました。
(もちろんこれはぼくがあくまで個人的に感じたメッセージです。映画の製作陣がそう思っていたかどうかはわかりません)
そんなメッセージは、実はミチを囲む三つの視点が絡み合って伝わってきたものです。
その三つの視点とは…
『プラン75』考察〜3つの視点がくれたもの〜ネタバレあり
以下の考察にもネタバレが含まれますので、ご自身の判断でお読みくださいね。
先にも書きましたが『プラン75』は、ミチが主役です。そして、ミチを取り囲むこととなる2人の人物=市役所職員のヒロム・プラン75コールセンターの遥子・「プラン75」施設職員外国人労働者マリア=それぞれ3人の視点が絡み合いながら物語が動いていきます。
この角谷を囲む3視点の絡み合いがベタベタせずに自然に進む様は見事でした。
それはひとえに早川千絵監督が練った脚本の素晴らしさだと感じました。
特に「プラン75」を普及させる市役所職員の役回りのヒロム役=磯村勇斗が、物語に深みを与えているなあ、と感じました。
では、一つ目の視点です。
一つ目の視点〜ヒロムの目
一つ目は、磯村勇斗演じる役場職員ヒロムの視点です。
ヒロムの仕事は、「プラン75」をすすめる窓口職員なわけですが、彼は人の生き死に関わる「プラン75」を、まるで介護保険や金融商品と同サービスのように、ナチュラルにすすめるんですよね。
その自然さが、怖いです。
磯村勇斗は「お役所ならではの一線引いた優しさ」を見事にまとい、演じきっています。
おっと、失礼!役場への悪口ではありません。でも、役場窓口って、会社窓口にはない、行政独特のスマイル空気って、あるじゃないですか。それですよ、それ。
磯村勇斗の市役所職員演技は、ほんと、ヨイです。見ものです!
さて、そのヒロムは「プラン75施設」の運営母体が産業廃棄物処理業者だと知って、一抹の疑問を感じるのですが、感じた疑問をセンセーショナルに問い叫ぶわけではなく、自分なりの行動をとり始めます。
その行動は、縁遠かった叔父の死に寄り添っていく行動となるのですが、その行動も、普通っぽくて、ヨイです。
寄り添っていった家庭で、命の絶えた叔父を自らの手で火葬に付すべく、「プラン75」施設からこっそりと運び出します。当然、役場職員が近親者の遺体を勝手に運び出すなど非合法な行動ですよね。
では、この行動が暗に示しているのは、なんでしょう?
それは、ヒロムが行政からの「ハミダシモノ」となった…ということでしょう。
しかし、ヒロムのとったハミダシ行動は「お役所ならではの優しさ」を越えた、人として真の優しさを勝ち取った男に変わっていくメタモルフォーゼだ、と、僕は感じました。
勝ち取った、なんて書くとヒロイックな感じがして誤解を与えるかもしれませんね。
ヒロムの行動にはヒロイック感がまったくなくて、とても静かなんです。
ですが、ぼくはそんな静かなメタモルフォーゼが、「人は疑問を感じたら静かにでも、ヒロイックじゃなくても行動を起こせるんだ」という監督からの隠れメッセージのように思えました。
では、次に二つ目の視点にまいりましょう。
二つ目の視点〜マリアの視点
二つ目に視点は、脇役として登場する外国人労働者マリアの視点です。
マリアは、低賃金にあえぐ外国人労働者という設定です。
彼女は家族を養わなければならない切実な現実があります。
そんなマリアが、より高い収入を得るために選んだ仕事は「プラン75」施設の職員となることでした。
確かに高い収入を得る職員ではあるけれど、仕事自体はいわゆる「クサイものにはフタ施設」の、フタの内側での仕事です。
異文化の中で苦戦する一人の女性マリアを登場させたことは、日本という、人類史上稀に見る清潔クリーンこのうえない国家のもつ「クサイものにはフタ」への批判でもあるでしょう。
劇中、マリアが主人公ミチと縁が触れ合うシーンは、ほんの僅かです。
しかしマリアエピソードが加わることで、『プラン75』からぼくは次のメッセージを受け取りました。
「一見クリーンに見える日本という国は、はたして本当にクリーンなのか?答えはNO。その裏側は腐敗と汚泥にまみれている国なんだ、、、」
では三つ目の視点へ移ります。
三つ目の視点〜瑶子の視点
「『プラン75』の脚本はホント、よくできているなあ、、、」
ぼくは『プラン75』のあちこちでそう感じたのですが、その一つが、『プラン75』のコールセンターの存在をしっかり設定していることです。
コールセンターでのキーマンは、若い女性の遥子です。その遥子の視点が三つ目です。
遥子はコールセンター職員….多分、ヒロムとは違い契約職員なんですが、彼女のドラマの中での存在が、大きな歯車となっています。
ぼくらの日常でも、高齢者への関わりが当たり前になってきていますよね。
そんな高齢者と若者の会話のズレや、逆に若者の持つ優しさを、表現しているようにも思えました。
さらにいうなら、「主人公ミチがどんな過去で、どんな人なのか?」が、より観客に深く伝わってくるのは、遥子との電話での会話からなのです。
いくつかのミチと話す遥子のシーンから察するに、若い遥子は、多分核家族で育ち、祖父母との交流もさほどなかったんだと感じます。
ミチは独居老人となり話す相手がいなくなり、結果的にコールセンターの遥子のみが社会との繋がりとなってしまいます。
そこで交わされる会話でミチも救われるのですが、逆に遥子は、それまでに考えてもいなかった新たな思索を得ることになります。
思索をもたらしてくれた相手が、今から死に向かう老人なのです。
逆にいうならば、遥子の存在がぼくらに教えてくれるのは、一見孤独で、死を目前にした人間でも、誰かと関わっていて、誰かに影響を与えているのだ、ということではないでしょうか。
ミチは知らず知らずのうちに目に見えない影響を与えていたのです。
しかし、そんなミチの「その後」がとても気になりつつも、観客の想像に任せて終わっていくのがこの映画です。
『プラン75』ラストの「その後」を考える
『プラン75』を見終わって、誰もが「ミチのその後」に思いをはせずにいられないと思います。
だって、身寄りもお金も、収入源もないゆえにミチは「プラン75」で一旦は死を選んだのですから。
そんなないないづくしのミチが、「それでも生きてみよう」と考えたわけです。
生活保護を受けながら生きていくことを選んだのだろうか??と安易に考えましたが、おいおい、それは安易だろう、、、ラストのミチが口ずさむ歌が答えなのでは?と、歌われる「林檎の木の下で」がどんな歌詞なのかを調べました。
「林檎の樹の下で」はこんな歌詞です
林檎の樹の下で
明日また会いましょう
黄昏 赤い夕日
西に沈む頃に
楽しく頬寄せて
恋をささやきましょう
真紅に燃える想い
林檎の実のように
「林檎の樹の下で」の歌詞から推測するその後
ミチはラスト、黄昏の夕日に染まりながらこの歌を口ずさみます。
まさに、ミチは、この歌から、残されている時間はあと僅かではあるけれど、「人生という恋」をささやき続けることが、自分が生きた証になる、と思ったのではないでしょうか?
林檎の実は熟し切ると、ポトリ、と落ちます。
ミチは、たとえ生活保護を受けたとしても、路上生活者になろうとも、ポトリと落ちるその時まで、「明日の太陽に会おう」と思ったのだ、と、ぼくは思っています。
『プラン75』は怖い?意味不明?実現してほしい?賛成?反対?
冒頭から最後まで一気見でした。観てよかったです。
『プラン75』ほど、世代や自分のいる環境で受け止め方が変わってくる映画は、なかなか無いのではと思います。
怖い?意味不明?実現してほしい?賛成?反対?ネット口コミはそれはもう陰陽混濁でしょう。
昭和の生まれか、平成に育ったかでも違うと思います。
両親が何歳か?でも違うでしょう。
祖父母と同居している人と核家族育ちでも全然違う感想を持つでしょう。
介護地獄に追われている人は、『プラン75』をいったいどう受け止めるのでしょうか?
そんなふうに、観る人それぞれで受け止め方は違ってくる映画が『プラン75』だと思います。
でも、、、今の時代、大事なのは「多様性を認めること」であり「まずは声を発すること」でもありますよね?
「あなたはどう思いますか?」との問いが、どこまでも背中を追いかけてくる映画でした。
ちなみに高齢者介護のリアルに差し掛かってるぼく(介護する方です)は、自分の内面をざらざらやすりで擦られるようで、怖い映画でもありました。
『プラン75』評価は?
ロイターでのインタビューで監督がこんなことを話しています。
「いかに死を迎えるかは個人的なもの。それを国がコントロールする恐ろしさを表現したかった」。そして疑問も持たず制度を受け入れる人たち、携帯電話の契約のように淡々と「最期」の申請手続きを進める職員。「決まったことに従う、あらがっても何も変わらないという日本人的キャラクターも描きたかった」
見終わった後でこの記事を目にしましたが、監督の思いは映画を通してしっかり受け止めていたな、と感じました。
ぼくの評価は星四つ⭐️⭐️⭐️⭐️です。
考えさせられるいい映画をありがとうございました。
『プラン75』配信先
2024年5月現在、Prime Videoで配信中です。
ブルーレイはこちらで購入できます


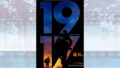

コメント