『ダンケルク』登場人物のリアルな心象と時系列考察
評価:星五つ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
『ダンケルク』はに作品ありますが、今回取り上げるのは1917年公開の作品です。監督・脚本は常に独自路線を貫くことで有名な名匠クリストファー・ノーラン。描かれる舞台は第二次世界大戦のフランス・ダンケルクの海岸。戦史としても有名な「ダンケルクの戦い」を描いた作品です。
「ダンケルクの戦い」とはドイツ軍がフランスに侵攻した1940年5月24日から6月4日の間に起こった撤退作戦です。ダンケルクの海岸に包囲されたイギリス。フランス両軍は、風前の灯でした。チャーチル首相は『ダイナモ作戦』を発動。駆逐艦はもとより、民間小型艇、民間船舶まですべての港にある船を動員して、40万人の将兵をイギリス本国に脱出させました。
クリストファーノーラン監督はその撤退作戦を、陸海空それぞれの兵士の目線と独特な時系列描写によって今までなかった戦争映画表現を試みています。撮影監督の手腕も存分に発揮され、IMAX上映されました。
ヘンな言い方ですが、美しい戦争映画です。そんな『ダンケルク』をぼくなりの感想と時系列解説を交えてレビューしてみます。
第90回アカデミー賞で編集賞、録音賞、音響編集賞を受賞しています。(英・米・仏・蘭合作:1917年公開作品)
『ダンケルク』解説〜どんな映画?
『ダンケルク』あらすじは?
あらすじは、Wikipediaのテキストを改稿して紹介します。
第二次世界大戦初期の1940年5月26日 – 6月4日。イギリス、ベルギー、カナダ、フランスから成る連合軍将兵は、フランスのダンケルク海岸でドイツ軍に包囲され、海峡を挟んだイギリス本土への撤退を余儀なくされた。
主人公はイギリス陸軍の二等兵の若者だ。彼は分隊が全滅し、ひとり撤退作戦中のダンケルクの砂浜に辿り着く。桟橋にはイギリスの救助船が接岸し、乗船を待つイギリス兵が列をなしている。
若者は遺体を砂浜に埋葬していた無口な兵士と出会い、負傷兵を乗せた担架を担いで救助船に乗り込むが、出港して間もなく同船は撃沈。若者はなんとか脱出する。
時同じくして、イギリス側の港町ではダンケルクの兵士を救う為に、海軍が民間船の徴用を始めていた。
その港に一艘の小型船がもやわれている。船主は初老の退役軍人ドーソンだ。息子のピーターもサポートとして同行させている。ピーターの友人の年端の行かない若者ジョージも無理やり乗船、船は港から出航する。
強引な出航には理由があった。実はドーソンの息子は空軍に入隊し戦死、自分たちの世代が戦争を決めたことで若者が死にゆく状況に心を痛めていたのだ。
途中、ドーバー海峡の海上で一人の英国兵士を救助するドーソンたち。船がダンケルクに向かうと聞いた兵士は、「戻らない! 英国に向かえ!」とパニックを起こし、争いの中でジョージが重傷を負う。
また、時同じく、イギリス空軍パイロットのファリアは、小隊長とコリンズの3機のスーパーマリン スピットファイアで、ダンケルク撤退作戦の援護に出撃する。
ファリアの小隊は、途中ドーバー海峡上で敵と遭遇。メッサーシュミット一機を撃墜する。しかし隊長機は撃墜され、コリンズ機も被弾し海上に不時着する。コリンズはドーソン艇に救助される。一機残ったファリアはダンケルクへとむかい、敵機と交戦する。
舞台はダンケルクの砂浜に戻る。
撃沈された船から辛くも脱出した二等兵の若者が、助かった仲間と砂浜に座り込んでいる。
そこに通りかかるハイランダー連隊の兵士たち。彼らは連隊に合流し、浜辺に座している小さな貨物船に乗り込む。満潮で船が浮けば脱出できる…そんな小さな希望にすがり満ち潮を待っていたが、船はドイツ兵の射撃で穴だらけになり海水が浸水。浮くことが叶わずに全員が貨物船を捨てる。
次々と絶たれる希望…。果たして英国兵たちは無事祖国へと戻ることができるのか???
『ダンケルク』あらすじ結末ラストまで〜ネタバレ閲覧注意
以下は結末までのネタバレとなりますので、映画を観る方は閲覧厳禁です。
+ + +
あわやと思えたその時、ダンケルクの渚に民間の数えきれない小型船舶が押し寄せる。イギリス本土から海峡を渡ってきた英国船だ。中にはドーソンの船も見える。
彼らは乗せれる限りの兵士たちを船に乗せる。しかし、そんなさなか、重傷を負っていたジョージの命の火は消える。ドーソンはさまざまな思いが入り混じった表情で英国本土へと舵を切る。
空ではダンケルク上空で英国軍を守ったファリアのスピットファイアが滑空している。燃料切れだ。ファリアはダンケルクの砂浜にスピットファイアを着陸させ、ドイツ軍の捕虜となった。
港に着いたドーソン艇。大勢の兵士が疲れ切った表情で岸壁に上がる。
不名誉な撤退に、英国本土では罵倒を浴びせられるとばかり思っていた兵士たちは、市民や退役軍人たちからジャムを塗ったパン、そして紅茶を差し伸べられ、優しく暖かく迎えられる。
陸に上がったドーソンの息子ピーターは地元の新聞社の扉を叩く。
数日後、新聞には命を落としたジョージの写真が載っていた。紙面には「命をかけてドーバー海峡に出向き、英国兵救出に当たった英雄」としての文字が大きく載っていた。
エンドロール
『ダンケルク』解説 事実をベース噛み合う3つの時間軸
3つの時間軸とは?
「ダンケルクの撤退」は戦史上有名な事実です。その事実をクリストファー・ノーラン監督自身が脚本をかき、一本の作品に仕上げました。事実ベースではありますが、あくまで脚色された映画エンタティメントですからノンフィクションドキュメンタリーではありません。
しかし史実をもっともらしく見せる撮影カメラマンの腕や、陸、海、空それぞれの違った時間推移を同時進行で描くというクリストファー・ノーラン監督の脚本には驚きます。
撮影されたロケ地は撤退作戦の行われたダンケルクの海岸です。この点も作品リアリティに大きく貢献していると思います。(ちなみにノルマンディ上陸作戦をリアルに描いた戦争映画の傑作『プライベートライアン』のロケ地はアイルランドです)
陸、海、空それぞれの違った時間推移を同時進行で描くという点についてですが、「陸は一週間」。「海は1日間」。「空は1時間」の出来事になっています。その時間は、陸海空のシーンが始まる冒頭にテロップでインサートされます。
観客はここで「陸は一週間」。「海は1日間」。「空は1時間」の出来事なのだ、と、すぐにストーリーのの脈を理解できるか?というと、、、たぶんそうではないでしょう。
およそ監督のそんな時間軸を分けた意図を観客がハダで分かり始めるのは、途中から、でしょう。そして見終わって思うのです。「そうか、初めから同時進行していたんだ」と。少なくともぼくはそうでした。
そんなわけで、ぼくは『ダンケルク』の二度見をおすすめします。
「ダイナモ作戦」という時計の針を動かす3つの歯車
チャーチルが「ダンケルクに包囲された兵士たち40万人全員を、総力あげて救出させるぞ」と命じたのが「ダイナモ作戦」です。
海、空、陸を追うカメラで描かれるこの映画を2度目にみると、3つのドラマが一つになっていく様が、まるで正確な時計の針のように感じます。
そう、「救出を待つ陸軍兵卒たちの一週間」、「海上で救助に向かう民間船の1日間」、そして「空からの援護に向かう空軍パイロットの1時間」は、大きさの違う3つの時計の歯車であり、それらの歯車が緻密に噛み合って時計の針『撤退』へと動きを伝え、ラストへと進む映画が『ダンケルク』なのです。
なんとアーティスティックな戦争映画でしょうか。
「アート」とは、ふだん意識していないことを他の側面から表現してオモテに表す作業です。
3つの時間軸を2時間という映画の中で見事に調和させた映画は、『ダンケルク』の他に観たことがありません。
有名なダンケルク撤退作戦を、誰も気づかなかった表現手法で見せてくれた『ダンケルク』は、アート作品と言っていいとぼくは感じています。
美しさを求めた戦争映画
「アーティスティック」という言葉を使いましたが、それは脚本のみに限りません。撮影、音楽、音響においても「美」が求められた結果が実を結んでいるのが『ダンケルク』です。
スピットファイアが3機、編隊をくみ空を飛ぶカットや列をなす兵士たちを浜辺にとらえたカメラの美しさは、絶品です。
そして常に映画の中で脇役として静かに、でも延々と流れる音楽のなんと心に迫ること。
3つの時間軸のみならす、脚本、映像、音の三つまでもが美しさとは何か?を意識しています。
ぜひ、美しさをこの映画に見てほしいとぼくは思います。
変な言い方ですが、「美」を探してこの映画を見直すと、1回目の鑑賞とは映画の印象がガラリと変わったものになったのです。(ぼくの場合は、ですが)
少ないセリフが描き出すリアルな心象
『ダンケルク』の特筆すべきことの一つは、「セリフが極端に少ない」という点です。
主人公の兵士はいますが、本当にセリフがありません。彼のセリフの数は、たぶん、両手で数えるくらいじゃないかと思います。
しかし、冒頭、銃撃から逃げ惑うシーンにしても、砂浜で救助を待つ兵士の列に迷うシーンにしても、「もし、自分が彼だったら」と考えると、セリフのなさが納得できます。
多分、恐怖や混乱に潰されそうになった時、人は何も言葉を発しないだろう、と思うのです。多分、観る人は意識の深いところでそのように理解してみてしまう。だからリアリティを感じるのだと思います。
ぼくは戦争を知りませんが、たぶん、様々な戦場があるんだと思います。
ダンケルクのような場にあって、人がどう言葉を発するか?
クリストファー・ノーラン監督はそこまでもちろん考えて脚本を書いたのではないでしょうか。
陸軍兵士たちのセリフのなさに比べ、比較的言葉が多いのは、兵士ではない民間人ドーソン、ピーター、ジョージの三人が乗る小型艇のシーンです。
その三人のドラマの中で、ノーラン監督は初老のドーソンに「自分たちの世代が始めた戦争で、関係のない若者たちが死んでいく。それがたまらない」といったセリフを言わせます。
極端にセリフが少ない脚本だからこそ、なおさらにその言葉がずっしりとした重みを持って響いてきます。
「ドーバーからきたのか?」との兵士の問いかけに込めた意味
クライマックス近く、ドーソンの船に救われた兵士が美しい夕景の中、こうドーソンに問いかけます。
「ドーバーから来たのか?」
「いや、ドーセットだ」
この二つのセリフが何を意味しているのでしょうか?
多分、問いかけた兵士は英国のどこかの田舎から出征した兵士なのでしょう。兵役に就くまでは、暮らしていた町の外など知らなかったに違いありません。かろうじて「ドーバー海峡」くらいは知っていた。というか、ドーバーくらいしか知らなかったと思うのです。なので、「ドーバーか?」と聞いた。
戦争が始まり、若者たちは突然に兵士仕立て上げられ、ヨーロッパ大陸に送られて、包囲されて、なんとか帰ってきた….そんな若い兵士たちは、戦争に出るまでは暮らしている町の外さえ知らなかったに違いないのです。
そう考えると、戦場に送られた若者たちの孤独感がリアルに迫ってきます。
ドーバー海峡に面してそそり立つホワイトクリフを見た兵士が呟いた小さなセリフから、ぼくはそんな孤独感を受け取っていました。
ちなみにドーセットとはドーセット州であり、ホワイトクリフよりもさらに西です。
ドーセット州にある港からダンケルクまでは、思いのほか距離があります。その距離は「一日の出来事」という時間軸をしっかり裏付けています。
『ダンケルク』考察1・なぜ「つまらない」と感じるのか?
多分、アクション激しい戦争映画を期待して『ダンケルク』をみると肩透かしを喰らうと思います。もし「つまらない」と感じたならば、「登場人物が、もし、自分だったら…」と、視点を置き変えて観ることをおすすめします。
冒頭で主人公の二等兵は、誰もいなくなった街路で突然に銃撃にあいます。慌てふためき逃げ惑います。そこで「彼がもし、自分だったら、、、」と視点を変えて観るんです。
そうするとこの映画はつまらないどころか、心臓がハクハクするほどの怖さで迫ってくると思います。
視点を変える、立ち位置を変えて観る。すると映画は意外にも違った風に見えてくると、ぼくは思っています
『ダンケルク』考察2・スピットファイアとイギリスドーバーの白い崖
ドーバー海峡には真っ白い断崖絶壁が延々と続いています。劇中にもその崖は少し登場しますが、断崖が何でできているかというと石灰岩です。
ぼくはホワイトクリフが憧れの地の一つで現地に旅したことがありますが、断崖の上でその石ころを拾ってきました。その石は真っ白で柔らかく、本当にチョークのように書けるのです。
スピットファイア戦闘機が白亜の断崖をバックに飛ぶシーンは本当に美しいシーンですが、パイロットのファリアがチョークで飛行時間を機内で書き留めるシーンが出てきます。
そのシーンに何が隠されているのでしょうか?
ここからはぼくの推測です。
英国人のスピットファイア戦闘機に対する愛は、祖国を守った戦闘機として、日本人には理解できないほどの熱があります。いまもイギリスでは土産物屋などでスピットファイアグッズが並べられています。
加えて、ファリアが手にしているチョークは、その原料となる石灰岩から、堅固な砦としてホワイトクリフ、また、英国人のプライドでもあるホワイトクリフを暗に表現しているのだと推測しています。
スーパーマリンスピットファイアとチョーク。
何気に結びつかない戦闘機と筆記用具ですが、この二つのモチーフからぼくは否が応でも「祖国を守った砦と飛行機へのリスペクト」を感じてしまうのです。
そういえば、頭上を飛んでいくスピットファイアのエンジン音を一発で聞き当てたドーソンのセリフにもこんな一言があります。
「ロールスロイスのエンジン音はすぐにわかる。最高の音だな」
このセリフにも、英国人のスピットファイアへの熱いラブが込められています。
『ダンケルク』考察3・クリストファーノーランの祖国愛
三つの時系列を巧みに組み合わせたこの映画で、クリストファー・ノーラン監督が何を伝えたかったのでしょうか?
戦争の無情さでしょうか?
助ける尊さでしょうか?
もちろんそれらも大事なメッセージだと思います。しかしそれ以上にこの映画を通して伝えたかったことは、祖国への敬愛だとぼくは感じています。
何度かいくつかのシーンで、英語で『HOME』という言葉がセリフに使われます。
この『HOME』は、家という意味が一般的ですが、字幕では『国』や『守るべき祖国』といったニュアンスで表現されています。
ひるがえって、ぼくは『祖国への愛』という意味にも取れました。
クリストファー・ノーラン監督はハリウッドで活躍していますけど、生粋のイギリス人です。
空を飛ぶスピットファイアの三機編隊の超絶な美しさや、ドーソンたちの気概、助けられてイギリス本土に戻った兵士たちを迎える、第一次世界大戦の戦傷退役兵と思われる盲目の男。そして、のどかな田園風景は、それこそひとつひとつが、「祖国愛」という名の時計の裏蓋の中におさまったいくつもの歯車なのです。
「国を愛するとはこういうことさ」と映画を通して言われたような気がしました。
『ダンケルク』ぼくの評価は?
ぼくの評価は星五つ🌟🌟🌟🌟🌟です。
『ダンケルク』は戦争映画とジャンル分けされていますが、これまでの他の映画にはない美しさに満ち満ちています。
この美しさとは単純に「きれいだね」という美しさとは違います。
1時間半という映画の時間の中に写し込まれているのは、風景の持つフォルムの美しさから、人間の行動の美しさや、意思の美しさまで、幾つもの美です。
『ダンケルク』は、戦争を題材に美を問いかけた、稀有な映画だと思います。
是非、それぞれの視点で『ダンケルク』の中に美を探してほしいと思います。
『ダンケルク』配信先
U-Next で配信されています。


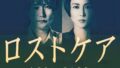
コメント